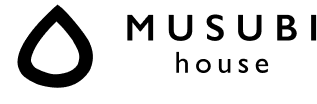9月1日は「防災の日」です。この日は、関東大震災をきっかけに作られ、地震や台風などの災害に備える大切さを考える日として広く知られています。
ペットの災害対策については、環境省が2018年に発行した「人とペットの災害対策ガイドライン」が基本指針になっています。改めてこの冊子を読み直してみると、災害時にどう行動すべきかを考える助けになるでしょう。
このガイドラインでは、たとえば「自宅に住み続けられる場合」や「避難所に行かなくてはならない場合」など、さまざまな状況を想定しています。
しかし最近の調査で、こうした想定だけではカバーしきれない飼い主の複雑な気持ちや、準備の足りなさが浮き彫りになってきています。
- ペットと一緒に入れる避難所を知っている飼い主は、わずか13.7%(バイオフィリア調べ)
- 避難所で「同じ空間で過ごせない“同行避難”」は 84%が利用しない と回答
- 一方で「同じ空間で過ごせる“同伴避難”」であれば 72%が利用する と回答
- 92.7%の飼い主が「備えに不安」 を感じており、半数以上(52.9%)は「備えが不十分」と回答(ユニ・チャーム調べ)
- 実際にローリングストック(食品を少し多めに買い置きし、 賞味期限内に古いものから消費しながら買い足す保管方法)を実践している人は 36.4% にとどまる
こうしたデータからも、ペットの防災については「知っていること」と「実際に備えていること」、そして「いざというときに行動できるか」の間に、大きなズレがあることがわかります。
身近なところから始めるペット防災
ペットと人が災害を乗り越えるための対策は、身近なところでできることがたくさんあります。先述のガイドラインにも具体的な行動指針がありますが、その他、住まい方に関して下記等が考えられますので参考にしてみてください。
<防災を意識した住まい方>
- 備蓄品を整理でき、フード・水・薬・トイレ用品等をすぐに持ち出せる専用スペースを設ける
- 日常の収納動線に「ローリングストック」を取り入れやすい仕組みをつくる
- ケージ、クレートに慣れさせるために日常的に使える場所に置く。
上記の実現のために、収納計画における備蓄品の優先順位を上げたり、収納家具のレイアウトを変える、家具を新調することなどが考えられます。猫の立体ケージは防災の視点からも用意することが好ましいでしょう。
また阪神淡路の震災でも地域の連携が大きく取り上げられました。下記も日ごろから意識しておくとよいでしょう。
<地域で行う防災活動>
- 「ペットと一緒の避難訓練」や「防災ワークショップ」等への参加
- 専門家や地域コミュニティと連携し、災害時の行動計画を共有
まとめ ー 災害時に大切な“離れない”避難
調査結果からも明らかなように、多くの飼い主は「ペットと同じ空間で避難できるか」を重視しています。家づくりという視点からは、在宅避難ができる堅牢な耐震性、電気やガスが止まっても寒さ暑さをしのげる断熱性等の高いスペックを確保することで実現します。
MUSUBI houseは、高性能で、安心できる暮らし方ができる家をご提案し、“ペットと離れない防災” を可能にし、併せてワークショップ等で地域の防災活動の一助になりたいと考えています。
9月1日の防災の日をきっかけに、ぜひ「ペットと一緒の備え」を見直してみませんか?