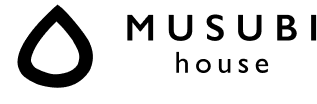ペットの絆が「命を守る力」に
―災害時の“愛”のレジリエンスとは?

災害が発生して避難するか迷ったとき、避難先で心細い夜を乗り越えたとき、そのそばには、静かに寄り添ってくれる存在がいた———災害時に「ペットとの絆」が人を動かす力になることを示した研究があります。
2014年に『Animals』誌に掲載された論文でオーストラリア・セントラル・クイーンズランド大学のトンプソン氏ら(Thompson ほか, 2014)は、 ペットとの関係性が与える避難や回復への影響を調査しました。
災害時に特に影響を受けやすい社会的弱者とされるグループ(先住民、移民、高齢者、子ども、障害者、ホームレス、精神疾患を持つ人々)を対象に研究を行った結果、「人は、ペットの存在によって“逃げる勇気”や“生き延びる力”を得る」ことが検証されました。
動物との深い絆は、災害時の大変な状況下で、人々の行動を変えるきっかけとなりうるのです。
ペットは「避難の障害」ではなく「生きる理由」
かつて災害現場では、ペットが「避難の妨げ」とされることもありました。たとえば、避難所が動物の受け入れに対応していないために避難をためらう、あるいはペットの救出中に人が巻き込まれてしまうといったケースがあることで、これまでは広く「ペットは災害時におけるリスク」と見なされてきました。
しかし現在では、動物との絆はむしろ災害への備えを促し、人の命を守る「保護因子(protective factor)」として注目されています。
トンプソン氏らの研究では、飼い主が避難することを後押しした要因として最も多く挙げられたのが、 「この子(ペット)を守りたいから」という意志でした。
研究によれば、動物が災害時に果たす役割は多岐にわたります。
- 避難の意思決定:「この子を置いていけない」から「一緒に避難しよう」へ
- 防災意識のめばえ:「この子もいることだし災害への備えをしなければ」
- 社会的つながり:ペットを通じた地域のつながりが、避難後の支えに
- 情報の伝達:ペット支援団体や動物病院などから防災情報が届きやすい
特に高齢者や障害のある方などが、ペットの存在によって避難を決めた事例も、多数見つかっています。
避難後の生活においても、ペットの存在が心の安定や生活の立て直しに大きな役割を果たしていることがわかっています。
「この子がいたから、絶望しなかった」
災害からの「回復期」においても、ペットは大きな意味を持ちます。
家や仕事を失っても、ペットがそばにいてくれたからこそ立ち直れたという声は少なくありません。ペットの存在はストレスや不安を和らげ、孤独感を減らし、再び前を向く力を与えてくれます。
反対に、災害時にペットと引き離されてしまったことで、深い悲しみや罪悪感に苦しんだという事例もありました。
人にとってペットは家族以上の存在であり、その喪失は深刻な心理的影響を及ぼすのです。
だからこそ、災害時にもペットと一緒に避難できる体制が、命と心の両方を守るために不可欠です。
「人とペットが、安心して避難し、共に暮らせる」住まいへ
ペットとの共生を前提とした住まいづくりにおいては、災害時における共避難や防災行動を支援する視点が重要です。近年では、ペットとともに安全に避難できる環境の整備や、飼い主同士が協力し合える体制づくりが求められています。
たとえば、
- ペットとの避難行動を想定した地域コミュニティでの訓練の実施
- 敷地内にペット同伴可能な一時避難スペースを設ける取り組み
- 災害時に備えたペット用のフードや日用品の備蓄、支援マニュアルの整備
などが挙げられます。
また、平常時から人とペットが快適に暮らせるよう、生活音への配慮、防音対策、開放的なリビング設計、飼い主同士・ペット同士が自然に交流できる共用空間の設計も重視されます。
ペットとの暮らしは「癒し」だけでなく、「命を守る力」となる可能性もある——MUSUBI houseもそのような考えを大切にし、防災と共生の視点を両立させた住まいづくりを目指していきます。
参考論文
Thompson, K., Every, D., Rainbird, S., Cornell, V., Smith, B., & Trigg, J. (2014). No pet or their person left behind: Increasing the disaster resilience of vulnerable groups through animal attachment, activities and networks. Animals (Basel), 4(2), 214-240. https://doi.org/10.3390/ani4020214